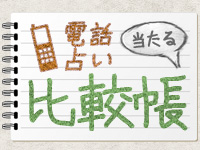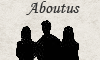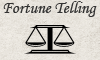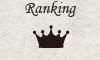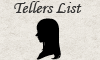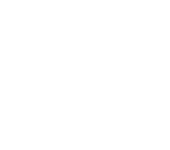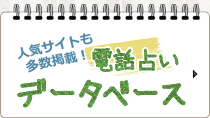占いの種類について
現在「占い」と称される術や方法は実に数多くの種類が存在します。
それは人の文明や文化と共に歩み、その多様化と同じ様に進化してきました。
このページでは「占い」の概念と歴史を体系にまとめて紹介していきます。
文明による占いの分類
最も広域にわたって広まっている占術である占星術は、ジョーティシュ(インド占星術)、ホロスコープ占星術(西洋占星術)風水や四柱推命、六星占術(東洋占星術)が有名です。 その期限は古代バビロニアを発祥とする説が有力でその後、ギリシア・インド・アラブ・ヨーロッパでそれぞれに発展した後に先ほどのような多様な形になったと考えられています。
また東西によってベースとなる考え方にも違いがあり、西洋占術の多くは、「火」「地」「風」「水」の自然界の四大要素を基本に構成されています。
それに対して東洋占術は「陰」と「陽」の二極、そして「木」「土」「火」「金」「水」という陰陽五行説をベースとして構成されています。
いずれも、自然科学的な概念を解釈してその考え方が整理されていった結果だと思われます。
手法による占いの分類
また、占いは手法によって命(めい)、卜(ぼく)、相(そう)、霊(れい)の4つの種類に分類されます。 "命"と"相"の占いは学問として体系化・データ化されている為に、学んで身につける事が出来ます。 これに対して"卜"や"霊"は、その占い・鑑定結果は、占い師が生まれ持った霊感やスピリチュアルパワーによって影響されるものになります。
目的による占いの分類

風水とは
この世を作っている「気」の流れを知り、それをうまく活用できるように調整すること。風水書の一節に、「気は風に乗って散じ、水によって蓄えられる」とあることから風水という名称が付けられた。 風水とはの詳細
易とは
卜術を代表する占術で、筮竹やサイコロなどから得られた卦により吉凶、運勢を判断する。 古代中国の伏犠(ふっき)が天地自然の万象をみて八卦を作り、八卦を重ねて六十四卦とした。易ではこの六十四卦が使われ、根本には陰陽思想がある。 易とはの詳細
九星とは
中国から伝来。陰陽道を通じ広まる、運勢や吉凶を占う基準。 一白・二黒・三碧・四緑・五黄・六白・七赤・八白・九紫の九つを指す。 これに五行と方位を組み合わせ、性格・運勢・家相などの吉凶を判断する。 九星とはの詳細
サビアンとは
ホロスコープを360度に細分化させ、それぞれの度数に対応するサビアンシンボルから占う占星術。 1925年にマーク・エドモンド・ジョーンズとエリス・フィラーの行った、360度に細分化された星座の度数からわき起こるイメージを記録するという実験が発端となる。 後に占星術師のディーン・ルディアによって、そのイメージを整理し新しい占術体系として築き上げられた。 サビアンとはの詳細
タロットとは
一般的には22枚の絵札からなる「大アルカナ(メジャー・アルカナ)」と、40枚の数札+16枚の人物札からなる「小アルカナ(マイナー・アルカナ)」の合計78枚のものが使われている。 タロットとはの詳細
Prev
1
Next